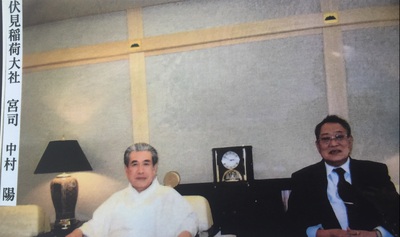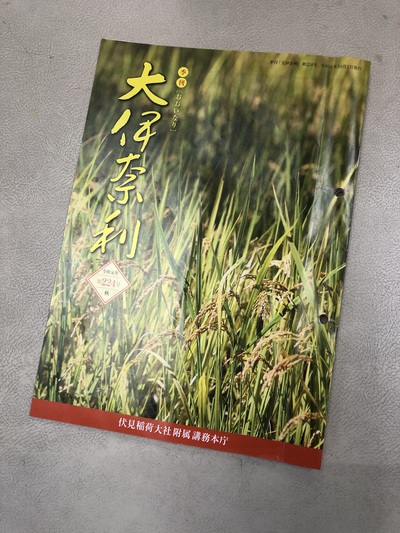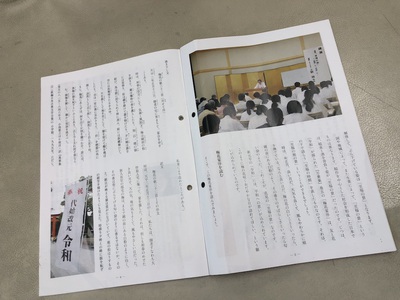雑感
新元号 令和について
2019年10月11日
新元号「令和」について、伏見稲荷大社広報誌「大伊奈利 第224号」に日本文学者(万葉学者)の上野誠先生のわかりやすい解説が掲載されていましたのでご紹介いたします。
(中略)
新元号令和 には、平和への思いが込められています。 梅の花咲くおだやかな日が訪れてほしい、という願いが込められているのです。
萬葉集 梅花の歌 32首(併せて序)
天平2年正月13日、師老(そちらう)の宅に集まりて、宴会を申すことあり
時は、初春の[令}月にして、気淑く風[和]ぎ、
梅は鏡前(きやうぜん)の粉を披きて、蘭は珮後(ばいご)の香を薫らしたり。加 以、(しかのみにあらず) 曙の嶺には雲移り、松は羅(うすもの)を掛けて蓋(きぬがさ)を傾けたり。夕の岫(くき)は霧を結び、鳥は穀(うすもの)に封ぢられて林に迷ふ。
庭には新蝶舞ひて、空には故雁帰りたるをみゆ。
ここに、天を蓋(くぬがさ) として土を坐(しきもの)として、膝を促(ちかっけ) けて觴(さかづき)を飛ばしたり。言(こと)は一室の裏に忘れさられて、衿(ころものくび)を煙霞(えんか)の外に開く。淡然として自ら放(ゆる)し、快然(くわいぜん)として自ら足りぬ。
もし、翰苑(かんえん)にあらずれは、何を以(もち)てか情(こころ)を攄(の)べむや。
詩には、落梅(らくばい)の篇を紀(しる)すといふことあり。古(いにしえ)と今と夫れ何ぞ異ならむ。園梅を賦して、聊かに短詠(たんえい)を成すべし。
(巻五の八一五~八四六序文、小島憲之ほか萬葉集・小学舘、1995 年。ただし、私意により改めたところがある。)
訳文
梅花の歌 三十二首とその序文
時は、天平二年正月十三日のこと。私たちは、師老(そちらう)すなわち、大伴旅人宅に集って、宴を催した。
それは、折しも初春のめでたき良い月で、天の気、地の気もよきて、風もやさしい日だった。
旅人長官の邸宅の梅は、まるで鏡の前にある白粉のように白く、その香りは帯にぶら下げる匂いの袋のように香りではないか。
その上、朝日が映えたる嶺は雲がたなびいて、庭の松はうすものの絹笠を傾けたようにも見えた。時移り夕映えの峰に眼を転ずれば、霧も立ちこめて、
鳥たちは霞のうすぎぬのなかに閉じこめられて、園林の中をさまよい飛ぶ。一方、庭に舞い遊ぶのは今年命を得た蝶だ。
空を見上げると昨秋やってきた鴈たちが帰ってゆくのが見える。この良き日に、私たちは天を絹笠とし、
大地を敷き物にして、気の合った仲間たちと膝を交えて酒杯を飛ばしあって酒を飲んだ。
かの宴の席、一堂に会する我らは、言葉すらも忘れて心と心を通わせ、けぶる霞に向かって襟をほどいてくつろいだのだった。
ひとりひとりのとらわれない思いと、心地よく満ち足りた心のうち。
そんなこんなの喜びの気分は、詩文を書くこと以外にどう表せばよいというのか。
かの唐土には、舞い散る梅を歌った数々の詩文がある。
昔と今にどうして異なるところなどあろうぞ。
さあ、さあ、われらも「園梅」という言葉を題として短歌を詠み合おうではないか・・・・・。
「令和」という元号は、『万葉集』巻五に収められている梅花の歌三十二首に付された序文の一節、「初春の令月にして、気淑く風和らぎ」(初春令月、気淑風和)の「令」と「和」の文字から採られています。
じつは、この序文の作者については、記されていません。大伴旅人説や山上憶良説などがありますが、不明としかいいようがありません。しかし、ここで大切なことは何かといえば、むしろ作者を記さないことの方なのです。もちろん、誰かが書いた文であることは間違いないのですが、記さないことにこそ意味があるのです。なぜならば、この序文は、大伴旅人の邸宅の梅見の宴に集まった、すべての人びとの気持ちを代表して書かれているからです。ですから、作者の名を記さない方がよいのです。
(上野誠氏の書き下ろしより)
10月22日には、天皇陛下の即位礼正殿の儀が行なわれます。
世界情勢、頻発する異常気象や天災、困難もまた多い昨今ですが、新元号「令和」の名の通り「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」明るく幸せな世になることを祈りつつ。。。

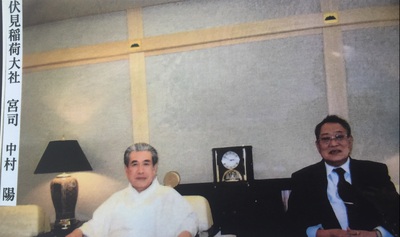
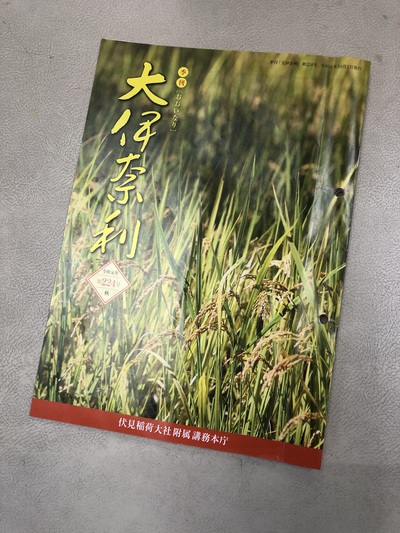
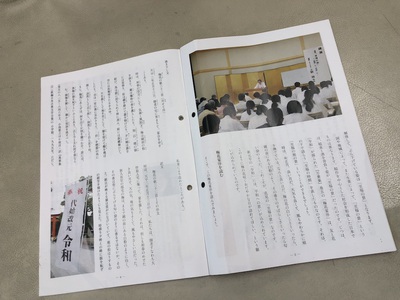
(中略)
新元号令和 には、平和への思いが込められています。 梅の花咲くおだやかな日が訪れてほしい、という願いが込められているのです。
萬葉集 梅花の歌 32首(併せて序)
天平2年正月13日、師老(そちらう)の宅に集まりて、宴会を申すことあり
時は、初春の[令}月にして、気淑く風[和]ぎ、
梅は鏡前(きやうぜん)の粉を披きて、蘭は珮後(ばいご)の香を薫らしたり。加 以、(しかのみにあらず) 曙の嶺には雲移り、松は羅(うすもの)を掛けて蓋(きぬがさ)を傾けたり。夕の岫(くき)は霧を結び、鳥は穀(うすもの)に封ぢられて林に迷ふ。
庭には新蝶舞ひて、空には故雁帰りたるをみゆ。
ここに、天を蓋(くぬがさ) として土を坐(しきもの)として、膝を促(ちかっけ) けて觴(さかづき)を飛ばしたり。言(こと)は一室の裏に忘れさられて、衿(ころものくび)を煙霞(えんか)の外に開く。淡然として自ら放(ゆる)し、快然(くわいぜん)として自ら足りぬ。
もし、翰苑(かんえん)にあらずれは、何を以(もち)てか情(こころ)を攄(の)べむや。
詩には、落梅(らくばい)の篇を紀(しる)すといふことあり。古(いにしえ)と今と夫れ何ぞ異ならむ。園梅を賦して、聊かに短詠(たんえい)を成すべし。
(巻五の八一五~八四六序文、小島憲之ほか萬葉集・小学舘、1995 年。ただし、私意により改めたところがある。)
訳文
梅花の歌 三十二首とその序文
時は、天平二年正月十三日のこと。私たちは、師老(そちらう)すなわち、大伴旅人宅に集って、宴を催した。
それは、折しも初春のめでたき良い月で、天の気、地の気もよきて、風もやさしい日だった。
旅人長官の邸宅の梅は、まるで鏡の前にある白粉のように白く、その香りは帯にぶら下げる匂いの袋のように香りではないか。
その上、朝日が映えたる嶺は雲がたなびいて、庭の松はうすものの絹笠を傾けたようにも見えた。時移り夕映えの峰に眼を転ずれば、霧も立ちこめて、
鳥たちは霞のうすぎぬのなかに閉じこめられて、園林の中をさまよい飛ぶ。一方、庭に舞い遊ぶのは今年命を得た蝶だ。
空を見上げると昨秋やってきた鴈たちが帰ってゆくのが見える。この良き日に、私たちは天を絹笠とし、
大地を敷き物にして、気の合った仲間たちと膝を交えて酒杯を飛ばしあって酒を飲んだ。
かの宴の席、一堂に会する我らは、言葉すらも忘れて心と心を通わせ、けぶる霞に向かって襟をほどいてくつろいだのだった。
ひとりひとりのとらわれない思いと、心地よく満ち足りた心のうち。
そんなこんなの喜びの気分は、詩文を書くこと以外にどう表せばよいというのか。
かの唐土には、舞い散る梅を歌った数々の詩文がある。
昔と今にどうして異なるところなどあろうぞ。
さあ、さあ、われらも「園梅」という言葉を題として短歌を詠み合おうではないか・・・・・。
「令和」という元号は、『万葉集』巻五に収められている梅花の歌三十二首に付された序文の一節、「初春の令月にして、気淑く風和らぎ」(初春令月、気淑風和)の「令」と「和」の文字から採られています。
じつは、この序文の作者については、記されていません。大伴旅人説や山上憶良説などがありますが、不明としかいいようがありません。しかし、ここで大切なことは何かといえば、むしろ作者を記さないことの方なのです。もちろん、誰かが書いた文であることは間違いないのですが、記さないことにこそ意味があるのです。なぜならば、この序文は、大伴旅人の邸宅の梅見の宴に集まった、すべての人びとの気持ちを代表して書かれているからです。ですから、作者の名を記さない方がよいのです。
(上野誠氏の書き下ろしより)
10月22日には、天皇陛下の即位礼正殿の儀が行なわれます。
世界情勢、頻発する異常気象や天災、困難もまた多い昨今ですが、新元号「令和」の名の通り「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」明るく幸せな世になることを祈りつつ。。。